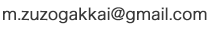刊行物
| 新出の高野大師四社明神画像について | 内田啓一 | 1 |
|---|---|---|
| タミルナードゥ州に現存する石彫仏像(調査報告) | 袋井由布子 | 1 |
| ジャワの金剛部系尊格の現存作例について | 伊藤奈保子 | 16 |
| シャル寺の曼荼羅壁画について(Ⅲ):プトゥンの金剛界曼荼羅理解 | 川崎一洋 | 37 |
| 「四種護摩本尊並眷族図像」における降三世マンダラ諸尊について:巻頭六尊の再検討 | 安元剛 | 48 |
| 双身毘沙門天小像の諸相 | 村田靖子 | 1 |
|---|---|---|
| 申生贅語:孝子伝図と孝子伝 | 黒田彰 | 17 |
| 鎌倉末期における涅槃図像の変容:誓願寺本を中心として | 加藤善朗 | 32 |
| 城陽市極楽寺阿弥陀如来立像について:仏師行快と快慶晩年の事績 | 近藤謙 | 46 |
| 密教論師としてのRatnakīrti:Śāsanasarvasvakasādhanaをめぐって | 桜井宗信 | 1 |
| バリ・ヒンドゥー寺院の神像について:バドゥブラン・プサ寺院の事例報告 | 山口しのぶ | 15 |
| 統一新羅:高麗前期の石塔における四仏について:東面の円形持物を執る如来像を中心に | 水野さや | 28 |
| アジャンター第2窟後廊左右祠堂のヤクシャ像について:王朝とヤクシャ信仰をめぐる問題 | 永田郁 | 48 |
| 魏陽贅語:孝子伝図と孝子伝 | 黒田彰 | 1 |
|---|---|---|
| 「西国三十三所順礼元祖十三人先達御影像」について | 白木利幸 | 19 |
| 中国における騎獅文殊と騎象普賢の成立と一対化過程に関する一試論 | 朴享國 | 1 |
| NāgabodhiのŚrī-guhyasamājamaṇḍa-lopāyikā-viṃśati-vidhiにおけるマンダラの度量法 | 田中公明 | 26 |
| いわゆるVajrācāryanayottamaについて | 苫米地等流 | 40 |
| Kriyāsaṃgraha所説の金剛界マンダラについて:枰線儀軌を中心として | 松尾力 | 51 |
| 北西インドにおける密教図像の展開:特に中国と西チベットへの流伝を視野に入れて | 安元剛 | 69 |
| インドネシアの財宝尊の現存作例について | 伊藤奈保子 | 100 |
| 山本兆揚翁と両界曼荼羅 | 真鍋俊照 | 1 |
|---|---|---|
| 韓国灌燭寺石造菩薩立像の特色に関する二、三の考察 | 岩崎和子 | 7 |
| 日本における不動明王の図像展開に関する一試論:特に頂髻を表す不動明王について | 見田隆鑑 | 22 |
| 総持寺所蔵銅板線刻蔵王権現像の再検討:刻字面の解釈を中心に | 太田雅子 | 42 |
| カーンヘーリー第三窟の初期仏陀像造例について | 平岡三保子 | 1 |
| 古代インドにおける蓮華手ヤクシャと観音菩薩の関係について:「ヤクシャの菩薩化」をめぐる問題 | 永田郁 | 16 |
| 中央チベットにおける不動の図像的な問題 | 大羽恵美 | 31 |
| 薬師寺の聖徳太子像と四天王寺の「泰川勝像」 | 石川知彦 | 1 |
|---|---|---|
| 金剛界八十一尊曼荼羅諸本に於ける各尊像の若干の相違について:五佛を中心に・制作側の観点から | 長谷法寿 | 16 |
| 但馬・今滝寺所蔵孔雀明王象の図像学的考察:中世日本における祈雨・孔雀経法の実践、そして思想をめぐって | 橋本愛子 | 28 |
| 北野天満宮所蔵「北野社絵図」に関する一考察 | 郷司泰仁 | 46 |
| アジャンター石窟における「従三十三天降下」の図について | 福山泰子 | 1 |
| スワート・カシュミール地域のブロンズ像の様式的源流について:パキスタン山間部の仏坐像を中心として | 安元剛 | 19 |
| 現存する「大清乾隆年敬造」銘の仏像群と宝相楼仏像群について | 那須真裕美 | 47 |
| 法隆寺再建をめぐる政治状況と五重塔塔本四面具 | 山岸公基 | 1 |
|---|---|---|
| 法隆寺五重塔塔本塑像西面の復原的考察 | 野村昌弘 | 17 |
| 法相曼荼羅の諸相とその系譜について | 多川文彦 | 31 |
| 胎蔵曼荼羅第三重の成立過程 | 田中公明 | 1 |
| 中央チベットにおける八大菩薩と併置される仏と守門神 | 大羽恵美 | 13 |
| ヤッカウランダ周辺の仏教遺跡 | 井上陽 | 31 |
| 大理国時代の密教における八大明王の信仰 | 川崎一洋 | 48 |
| ガンダーラの「誕生」図にみる文化基盤 | 上枝いづみ | 62 |
| 新出の同形同寸の銅製不動明王立像について | 村田靖子 | 1 |
|---|---|---|
| 蓮華三昧院所蔵阿弥陀三尊像について | 高間由香里 | 15 |
| 「ナーマサンギーティ文殊」の図像と典拠についての一考察 | スダン・シャキャ | 1 |
| 北西インドにおける『大日経』系毘慮遮那と三部の作例について:アジアにおける、図像と思想の展開を視野に入れて | 安元剛 | 22 |
| ハリプルの四仏について | 田中公明 | 48 |
| ジャワの浮き彫りと南インドの図像:「カメの空中飛行」の造形と文献の照応 | 松村恒 | 60 |
| 中国陝西省延安市安塞謙樊庄石窟について:陝北地方における北宋の石窟造営とその背景に関するてがかりとして | 水野さや | 69 |
| 善光寺式阿弥陀三尊の模像製作について:滋賀新善光寺の善光寺式阿弥陀三尊像を例に | 松岡久美子 | 1 |
|---|---|---|
| 山景をそなえた阿弥陀仏五十菩薩像について | 小野英二 | 18 |
| 『諸仏菩薩金剛等啓請』所収の「毘盧遮那修習啓請次第」について | 川崎一洋 | 32 |
| デーヴァとアスラの戦闘理由:パーリ語文献を中心に | 西谷功 | 1 |
| 『タントラ部集成』に収録される秘密集会曼荼羅について | 張雅静 | 22 |
| 天台大師智顗の肖像:延暦寺本をめぐって | 吉村稔子 | 1 |
|---|---|---|
| 平安時代前期・中期における孔雀経法の形成と展開:空海請来から藤原道長による平産の祈りへ | 橋村愛子 | 15 |
| 千手観音眷族の功徳天と婆藪仙をめぐって | 濱田瑞美 | 39 |
| 神変と光背に関する一考察 | 熊谷貴史 | 58 |
| 運慶壮年期における造形表現と造像環境について:興福寺木造釈迦仏頭を中心に | 植村拓哉 | 73 |
| トンワトゥンデンとは何か?:タンカの起源と『文殊師利根本儀軌経』 | 田中公明 | 1 |
| ギルギット地域・タルパンの陀羅尼刻文と、観音「随心呪」について:観音信仰からターラー信仰へ | 安元剛 | 10 |
| 密教図像学会三十周年記念中国仏教美術見学会:太原・五台山・応県・雲崗 | 頼富本宏 | 1 |
|---|---|---|
| 松島五大堂の五大明王象に関する一考察 | 見田隆鑑 | 20 |
| 仁海本仁王経曼荼羅の思想的裏付け:金剛利菩薩の三昧耶形を中心に | 鍵和田聖子 | 48 |
| Kambalapāda(La ba pa)『チャクラサンヴァラ成就法』:その構成と観想法 | 桜井宗信 | 1 |
| 韓国国立中央博物館所蔵の金銀製小型仏龕に関する一考察 | 瀧朝子 | 19 |
| チベットにおける四天王の図像について | 大羽恵美 | 33 |